1番打つ頻度が多いフォアハンドをもっと強化したいと思いませんか?
ほとんどの人は打った後にインパクトの面の向きや、手首の角度を気にすると思います。
あなたは手首の角度や使い方を意識していますか?
今回はフォアハンドを打つ中で、もっとも操作しやすい手首の使い方について紹介したいと思います。
動画でも解説しているので、参考までにどうぞ。
フォアハンドの手首の知識
手首の重要性
なぜ手首が重要かというと、ラケットにもっとも近い関節だからです。
地面からのエネルギーが運動連鎖で関節を伝わってくる最後の部分ということで、手首の使い方1つでエネルギーを最大限使えるか、無駄にしてしまうかに関わってきます。
せっかく作ったエネルギーが無駄になったら、手打ちなのと変わらないし、それだったら最初から手打ちの方が体力を温存できるかもしれません。
そのため、手首はしっかり脱力して、正しい動きをすることで、大きなパワーを余すことなくボールに伝えることができます。
手首は面の向きにも関わっている
また、手首はラケット面の向きに大きく関係してきます。
手首の使い方を間違えてしまうと、面の向きが変わってしまい、上を向いたり下を向いたり、意識してもしなくても変わってきます。
飛ぶ方向や距離が自分でわからないと、感覚的にも何が間違えていたのかわからないですよね。
手首の正しい使い方を覚えて、毎回同じようにできることが理想です。
フォアハンドの手首の動き
- 手首の背屈
- 手首の固定
- 手首をこねる
- 手首の脱力
この4つについて詳しく説明します。
手首の背屈でコックさせる
手首を甲側に曲げる動作です。手首の可動域を最大限に使うには、この形にすることが大切です。
インパクトでラケットヘッドを立てるなど、上に動かす動作をすることができます。
背屈させた手首は、インパクトに向かって、可動域のぎりぎりまで背屈されます。
限界まで背屈した手首は、その反動で元の位置に戻るので、1番加速した状態でインパクトすることができるんですね。
また、背屈させておくと、前腕の筋肉を使いやすくなり、インパクト後に必要な手首の返しを鋭くすることができます。
手首が伸びている状態だと前腕の筋肉を使いづらく、筋肉を使えないとボールをコントロールできなかったり、相手のショットの勢いに負けてしまうんです。
とくにインパクトで手首が前にいってしまうと、ボールの飛びを抑えられないどころか、手首をケガしてしまう危険があるので注意しましょう。
また、手首に無駄な力が入っていると、下半身から伝わってきたエネルギーがラケットにいく直前でストップしてしまうんです。
脱力しておけばスイングすれば勝手に背屈されるので、この背屈の動きは超重要です。
意識的な背屈はNG
注意としては、手首を意識的に背屈させるのは運動連鎖をストップさせてしまうので、あくまでも力を入れて背屈させるのではなく、始めから背屈の形を作っておいてリラックスした状態にしておくことが重要です。
人間の筋肉や関節は力を入れていない時こそ、可動域いっぱいの動きができるのです。
そのため、意識的に背屈させるというよりは、無意識に背屈する状態が正しい手首の使い方となります。
手首の固定で面を安定させる
手首を固定させることで、インパクトでラケット面の安定をさせることができ、ショットが安定します。
しかし、手首を固定させた場合の安定感というのは、ボールに勢いに出すことができないんですね。
1本のロープを想像してください。
そのまま振ったら、ムチのようにしなるので、先端に勢いがつきます。
一方、ロープが固まってたとします。しなりが生まれないため、先端でもそこまでの勢いがつけられません。
これと同じで、当てるだけなら固定することが大切ですが、ボールを飛ばす必要があるので、固定するのがいいことではありません。
また、鋭く振り抜いてこそスピンをかけることができ、安定したショットになるので、固定してしまうと鋭さを出すことができなくなります。
手首は感覚的に形を覚えさせて、力を入れて固定するのではなく、自然と力を入れずにその形にキープできるように目指しましょう。
手首をこねる
スピンをかけようとして、間違った動作の代表例がこねてしまうことです。手首をこねることは、ショットを安定させる上ではよくありません。
先ほどの説明で、固定もしくは振り抜くという安定感に必要な要素をいいました。
これは、振り抜いてスピンをかけていく動作だと思いますが、ショットは安定しないでしょう。
テニスのラリーにおいて、毎回同じショットがくることはありえないからです。
毎回同じなら、手首をこねたとしてもタイミングを合わせられるかもしれません。
ですが、毎回同じボールはきません。試合においては、コート全体を守る必要があるため、常に動かされるという条件がつきます。
ますますタイミングが合わない要素が増えてきましたね。
これでは、ショットを安定させることはできないし、ミスヒットを連発することになります。
少しでもタイミングがズレれば、浅くなって打ち込まれたり、抑えがきかなくてアウトします。
手首をこねるとケガに繋がる可能性がある
このミスヒットが続いたり、手首を酷使していると、ケガにもつながります。
手首は1度ケガをすると、打つ時の衝撃が全部伝わってしまうため、なかなか治らないので注意しましょう。
プロの選手でも、必要以上に手首をこねている選手はいません。
速くてわかりづらいと思いますが、こねているのではなく、前腕を使って振り抜いています。
手首はスイングの勢いで動いているだけなので、安定感抜群のショットが打てているのです。
>>手首が痛すぎてプレー不可能になったが、一瞬で治すことができた話
手首の脱力
スイングを鋭くするために必要なのが脱力させることです。
これは私も苦労しました。もともと常に100%で握っていたので、脱力の意味がわからず、習得に時間がかかってしまいました。
手首を脱力しようと思ったきっかけが、ショットのレベルをあげようと考えたからで、脱力することでスピンがかかり強打しても入るようになりました。
脱力して打つコツに関しては、【テニスの極み】フォアハンドを脱力して打つコツを参考してください。
なぜ脱力するとスイングが速くなるのかというと、先ほどムチにたとえた説明と同じですが、ムチにはなんの力もかかっていないので自由に動くことができます。
そのため、運動連鎖が先端に向かって伝わり大きなパワーを生み出すことができます。
それと同じで、運動連鎖で伝わったパワーをボールに伝えるために、手首に力が入ってはいけません。
なので、できるだけ力を抜くことがパワーロスなスイングをするための条件となります。
プロのほとんどは脱力している
ほとんどのプロの選手は、手首が脱力しています。そのため、あれだけのスイングスピードを実現でき、ショットが安定します。
手首は足や体幹に比べたら、力を入れやすくても、大きな力を出すことはできません。
前腕の筋肉は細いので、どう考えても足の筋肉に勝つことができないのです。
脱力すると、手首の角度が変わってしまうので、角度が変わりすぎない程度に自由にします。あとは反復練習で手首が形を覚えるまで練習するだけです。
手首の使い方の動画です。
ラケットを加速させるためのポイントがわかりやすいです。
フォアハンドの手首の正しい使い方
手首の動きを4つ覚えたところで、フォアハンドの手首の使い方について説明します。
手首の状態を説明すると、
- テイクバックで手首の背屈
- 背屈した時の形を固定(力を入れる訳ではなく脱力してインパクトの形を作る)
- スイングを開始すると、さらに手首が背屈される
- インパクトに向けて背屈していた手首が伸びてくる
- インパクトでボールを打った時に反射的に力が入る
- インパクト後に前腕をプロネーションさせる
この一連の流れが手首の正しい動きとなってきます。
先ほどの手首の動きで解説したことが全てですが、フォアハンド専用の動きがあるので、もう一度説明していきますね。
テイクバックで手首の背屈
テイクバックでは手首を背屈させるというか、インパクトの形を作ります。
インパクトの形ってわかりますか?
スイングを打点で止めてもらえればわかると思いますが、手首はインパクトの形のままテイクバックしていきます。
背屈した時の形を固定(力を入れる訳ではなく脱力してインパクトの形を作る)
次にテイクバックの形を力を入れずに、脱力したまま形を覚えさせます。
注意点は、力を入れて固定する訳ではなく、あくまで力を抜いて状態でインパクトの形をキープしてください。
スイングを開始すると、さらに手首が背屈される
インパクトの形をキープしていた手首は、スイングを始めるとラケットの重さでさらに背屈されたような形になります。
力が入っていると更なる背屈が起こらないので、脱力しておくのがポイントです。
インパクトに向けて背屈していた手首が伸びてくる
さらに背屈された手首は、インパクトを迎えたところで最初のインパクトの形に戻ります。
手首の形が戻る過程で勢いがついてるので、これでスイングスピードが一気に加速します。
インパクトでボールを打った時に反射的に力が入る
インパクトでは力を入れると言いますが、実は力が入るという言い方が正しくて、ボールを打った瞬間に反射としてラケットが飛ばされないようにグリップを握るというのが正解です。
そのため、ボールを打つまではラケットを握ることはありません。
インパクト後に前腕をプロネーションさせる
インパクトをした後は、インパクトの前に一度ラケットヘッドが下がるので、その状態からインパクトの形に戻ってくるため、自然とラケットヘッドが走ってきて、プロネーションされます。
プロネーションも脱力していないと起こらないので、本当に脱力はカギになってきます。
フォアハンドを強くするために手首を鍛えたほうがいいのか?
手首はあまり意識的に使うことはないけど、ある程度強化する必要があります。
強化することでどんなメリットがあるかというと、ベースが強くなるので脱力していても、筋力がある方のがパワーのあるストロークやサーブを打つことができます。
あと強いストロークを打つ時には、インパクトの衝撃が強いため、手首が弱いと耐えきれません。
自分のレベルが上がれば戦うステージも上がるので、結果的に手首が強くないとケガする可能性も出てくるんですよね。
ラケットの一番近い関節であり一番衝撃がくる場所なんで、しっかり鍛えておくことが重要です。
しかし手首だけを鍛えるというのも体全体のバランスを崩してしまうので、鍛えるなら大きな筋肉も鍛えた上で手首を強化していきましょう。
フォアハンドのしなりはラケットの重さも手首に影響している可能性あり
ラケットの重さについて確認したことはありますか?
男女差はあるものの、ラケットの平均は300gなので、今使っているラケットがどのくらいの重さか確認してみてください。
ラケットが重いと必要以上に力が入ってしまったり、軽いと必要以上の手首の動きをしてしまったりします。
極端に言えばバドミントンのラケットですよね。軽すぎて手首が動いてしまいます。
このようにならないためにもラケットの重さは重要なので、「脱力はできてるけどうまくいかないんだよな~」と悩んでる方は、思い切ってラケットを替えるのも1つの手段。
やはり使いやすいモデルは平均値になっていて、誰もが使いやすいモデルを黄金スペックなんて言ったりします。
「黄金スペックのラケットに変更したらうまくいった」という声は予想以上に多いので、ぜひラケットの変更も試していただけたらと思います。
とはいえ、黄金スペックと盲信するよりも、その人のレベルや体格に合ったラケットの重さというのがあります。
詳しくはこちら↓の記事を確認してみてください。
まとめ
手首については、ラケット面の向きに関わる部分として気になっている人も多いと思います。
フォアハンドの手首の一連の流れは
- テイクバックで手首の背屈
- 背屈した時の形を固定(力を入れる訳ではなく脱力してインパクトの形を作る)
- スイングを開始すると、さらに手首が背屈される
- インパクトに向けて背屈していた手首が伸びてくる
- インパクトでボールを打った時に反射的に力が入る
- インパクト後に前腕をプロネーションさせる
この流れをスムーズにやるためには、手首を脱力しておくことが重要です。
最初は意識するため、手首に力が入ってしまうこともあると思いますが、一球一球手首の動きを確認しながら打っていくと割とすぐに覚えられると思います。
脱力については、【テニスの極み】フォアハンドを脱力して打つコツを解説を参考にしてみてください。
とくにジュニアの場合は、手首が弱くケガしやすいので、体の大きな部分のエネルギーを使い、手首はリラックスした状態で打てるといいですね。
ジュニアにおすすめのトレーニング方法は、ジュニアの時にやるべき10のトレーニングで紹介しています。
また、フォアハンドの全体の説明に関しては、フォアハンドの打ち方を超わかりやすく解説!【初心者もOK】で説明しているので参考にしてください。
▼プロの試合を毎日チェック!
テニス LIVE 速報
▼ラケットに迷ったら参考にしてみて!
・男性におすすめのテニスラケットをレベル別に紹介!
・女性におすすめのテニスラケットをレベル別に紹介!
▼YouTubeをチャンネル登録で応援してね!
🎾ぼぶのテニスTV
今はこの動画がおすすめ!
打点が前にならない人は、この方法で確実に直せるからチェックしてみてね!


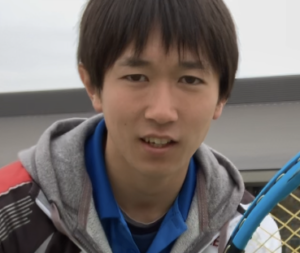
コメント